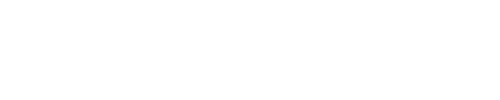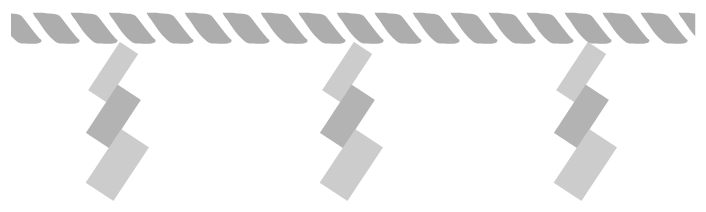
石下祇園まつりについて
石下祇園まつりの主催神は、本石下(もといしげ)の氏神 石下八幡神社と、新石下(しんいしげ)の氏神 石毛稲荷神社の2つです。
各々氏子総代を中心に参集し、本石下では八幡神社氏子総代1名、神事1名、自治区長7名、愛好会1名から祭りの3役員(委員長・副委員長・会計)が選ばれ責任者となり町内の協力のもと実施されます。新石下では、石毛稲荷神社の氏子役員によって、祇園祭実行委員会が組織され、新石下の15町内の区長を中心に、氏子の皆様の協力のもと実施されます。
石下祇園まつりの中心となるのは、本石下と新石下の二つの地区から繰り出される壮麗な大神輿です。
本石下の「千貫神輿」は明治初期に京の宮師によって作られた京神輿で、白丁(ハクチョウ)の装束姿は、白布の狩衣で高貴の方へ奉仕する支度から神輿装束として神輿と共にはるばる京から伝わったものといわれています。全国的にも稀な装束といわれ、その姿での多人数での渡御は、圧倒的な迫力があります。
対する新石下の大神輿は、揃いの伝統的な青法被に白足袋姿の担ぎ手たちによって力強く、威勢のいい担ぎ方となっています。
祭りは、隣り合う本石下地区と新石下地区で行われ、両地区の大神輿のほか、各町内の子供神輿十数基が集結します。大小それぞれの神輿が通りを埋め尽くすように練り歩く様子はまさに圧巻です。
また、祭り会場の交わる目抜き通りには、両地区の山車が背中合わせで置かれ、天神囃子やとんだやばやし保存会による深川ばやしが舞台で行われます。
山車が背中合わせで置かれる理由は、その昔、隣り合う本石下と新石下の大神輿の担ぎ手達が興奮し、神輿同士のぶつけ合いの喧嘩(喧嘩神輿)があったとされ、その後はお互いの縄張りに神輿が行けないようにしたと伝えられています。(諸説あり※1)
その喧嘩神輿の名残として新石下では、大神輿を山車にぶつけるという迫力の伝統行事が今なお受け継がれています。ぶつけた勢いで大きな山車が数メートル動くことも。
そして、祭りのフィナーレを飾る最大の見せ場として、最終日の20時頃には、それまで背中合わせ状態で、お互いに反対を向いていた山車が、正面に向き合い、激しく演舞を競い合う、突合せ(つっかせ)が行われます。突合せ(つっかせ)終了間際には、両方の山車の屋根に予め仕掛けられていた花火に火を着け、祭りは最高潮の盛り上がりを迎えます。
※1 石下の町は成り立ちからすると、本石下という地名のとおり、当初より発展していた市街です。その後、近代より現代となり駅や道路形態・インフラの整備等々から新石下も発展し、お互い競い合うようになったのではと思います。
そして、祭りの際も「本石下の神輿は北関東で一番大きい神輿だぞ。新石下のは小さいよな」といった雰囲気のなかで、大神輿の担ぎ手達が興奮し、神輿同士のぶつけ合いの喧嘩が毎年あったようです。どちらも立派な大きさの神輿ですから、すさまじかったと思います。やはり、神輿の大きさに分がある本石下に敵わなかったことを聞かされています。大きな神輿は担ぎ手も多く、新石下には不利だったようです。そこで新石下で編み出されたのが喧嘩トンボです。二本のトンボを長いものにして、相手のトンボが新石下の神輿本体に届く前に、相手神輿に突き刺そうという考えだったそうです。現在は長いトンボはありませんが、その後、同じように子供神輿にも伝承され、今はどこの町内の子供神輿も長いトンボを縛った神輿のスタイルになったとの話です。(諸説あり)
日本の歴史的背景
日本の各地で行われている祇園祭は、平安時代の京の都の祇園社・後の八坂神社から始まりました。これは、当時、平安時代の比較的初期のころの、西暦863年から869年の7年間に、日本が大きな災禍に立て続けに3度遭い、この災いを祓い清めるために神事として行った祀りごとが始まりです。この災いとは、西暦863年(貞観5年)京の都で、はやり病(疫病)が蔓延し多くの死亡者が出たこと。その翌年の864年(貞観6年)~866年には富士山の大噴火が起こり、文献記録に残るうちでは最大規模と言われ、大規模な溶岩が流出し大災害になったこと。そして更に、869年には、東北三陸沖で大地震(貞観大地震)が発生し、津波によって多くの犠牲者と、甚大な被害を受けたことです。この大きな災禍がたった7年のうちに起こったのです。 当時、疫病や災禍は、疫病により恨みを現生に残したまま亡くなった人々の怨霊の祟りと考えられており、その怨霊を鎮めなだめるために御霊会(ごりょうえ)を執り行い、その後、祇園祭と名を改められたものです。
日本各地への伝播
古代より、私達の住む日本は、四季に富んだ美しい山河・台地・海の自然から、多くの恵みを得て暮らしておりました。しかし、時にはこの多くの恵みを享受できる美しい自然が豹変し、多くの被害を人々に与えることもありました。このような中から、大いなる自然と人との接し方が変化していき、天と地の自然には恐れ多いそれぞれの神々がおり、畏敬・崇拝するものとされ、人々の心と結びつき神道として成立していったのです。
初午祭では、神社に神をお迎えし、宮司とともに、私達(氏子)は、五穀豊穣や平穏を祈願する神事を行い、また、秋の例大祭では、豊作の感謝を神々に捧げる神事を行うなどの、民衆の生活に寄り添う祭事が執り行われて、全国に広がり、受け継がれてきたものです。
全国に8万社あるといわれている神社では、今もなお、その継承を受け継いでおります。
中でも祇園祭は、各地で行われるようになり、またお国柄や時代背景等に影響を受けながら、各地方に浸透していきました。近代になり、江戸の華やかな、粋な出で立ちの神輿、威勢のいい掛け声、心地よいまつり囃子、等々は人々の元気の源となって、今では災いを祓い清める から 吹き飛ばすような勢いのある祭りとなっていったものと思われます。
(京都は伝統重視)
地方の村々への普及・組合等の形成
近代になり、各地の村々の人々は、組合や自治会を立ち上げ、特に若衆は、毎日続く、いつもの恒常的な生活から、若い力をたぎらせて感情を高揚させて行う、村祭りを行うようになりました。祇園祭は、まさにその中心にあったと思われます。